ユネスコ無形文化遺産
国指定重要無形民俗文化財
烏山の山あげ行事
山あげ祭
本文へ移動するお問い合わせ
- 那須烏山市 商工観光課
- 〒321-0692
栃木県那須烏山市中央1丁目1番1号 - 0287-83-1115
- 0287-83-1142
- 山あげ会館
- 〒321-0628
栃木県那須烏山市金井2丁目5番26号
山あげ会館(那須烏山市観光協会) - 0287-84-1977
- 0287-84-1978
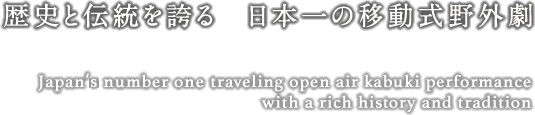
- ホーム
- 烏山の山あげ行事「山あげ祭」
- 山あげ祭とは
- 山あげ祭の日程【保存版】
山あげ祭の日程【保存版】
山あげ祭は、「烏山の山あげ行事」や「八雲神社の神輿」などで構成され、毎年7月の第4土曜日を含む金曜・土曜・日曜の3日間で行われます。
| 7月 |
ー | 1日 | |
|
祭 典 が 開 催 さ れ る 週 |
木 (祭典前日) |
||
|
金 (祭典初日) |
|||
|
土 (祭典中日) |
|
||
|
日 (祭典最終日) |
|
||
|
祭 典 後 |
翌日 |
|
|
| 31日 |
|
お注連立て
 この作業は八雲神社鳥居前に10メートル以上の齊竹を付け、ここから先は神聖な場所であることを示して、区域内では争いごとをせず、厄事などが入らないようにと結界を示します。午前7時に当番町の進行により祝詞奏上が行われ、神職、責任役員、当番町の八雲講世話人と全町の若衆達が鳥居前に集合します。当番町が粛々と作業を進め、仕事は厳粛、かつ正確さと迅速さが求められます。
この作業は八雲神社鳥居前に10メートル以上の齊竹を付け、ここから先は神聖な場所であることを示して、区域内では争いごとをせず、厄事などが入らないようにと結界を示します。午前7時に当番町の進行により祝詞奏上が行われ、神職、責任役員、当番町の八雲講世話人と全町の若衆達が鳥居前に集合します。当番町が粛々と作業を進め、仕事は厳粛、かつ正確さと迅速さが求められます。
奉告祭
 午後6時頃、当番町の奉賛講の人達が八雲神社の御神前に奉納の芸題を奉告し、併せて山あげ祭完遂の安全祈願の御祈祷を受けます。その後速やかに当番町の小屋台に芸題、当番町名を筆太に大書し、囃子方と共に全町を回ります。
午後6時頃、当番町の奉賛講の人達が八雲神社の御神前に奉納の芸題を奉告し、併せて山あげ祭完遂の安全祈願の御祈祷を受けます。その後速やかに当番町の小屋台に芸題、当番町名を筆太に大書し、囃子方と共に全町を回ります。
宵祭・笠揃(祭典前日)
 笠揃は当番町で行われる、いわゆる前夜祭です。正装した中老や若衆、子供達が金棒曳を先頭に屋台を会所前から自町内を一周して再び会所前に戻ります。到着したら若衆は素早く祭半纏に着替え、舞台を組み立てて山をあげます。神職によってお払いが行われ、それから会所開きとなります。関係者からの挨拶で始まり、金棒曳、若衆役職達の紹介が終了したら、いよいよ開演となります。(芸題:子宝三番叟)
笠揃は当番町で行われる、いわゆる前夜祭です。正装した中老や若衆、子供達が金棒曳を先頭に屋台を会所前から自町内を一周して再び会所前に戻ります。到着したら若衆は素早く祭半纏に着替え、舞台を組み立てて山をあげます。神職によってお払いが行われ、それから会所開きとなります。関係者からの挨拶で始まり、金棒曳、若衆役職達の紹介が終了したら、いよいよ開演となります。(芸題:子宝三番叟)
例祭・神幸祭(祭典初日)
 午前6時、多くの来賓や献幣使も参宮し、太鼓の音とともに祭礼が始まり、また太鼓の音と共に終了します。続いて行われる神幸祭とは、いわゆる出御の儀式です。八雲神社の社から大神様をお神輿に移し、お仮殿へと出御されます。担ぎ手は当番町で、ここでも機敏さが要求され、指揮を取るのは木頭です。
午前6時、多くの来賓や献幣使も参宮し、太鼓の音とともに祭礼が始まり、また太鼓の音と共に終了します。続いて行われる神幸祭とは、いわゆる出御の儀式です。八雲神社の社から大神様をお神輿に移し、お仮殿へと出御されます。担ぎ手は当番町で、ここでも機敏さが要求され、指揮を取るのは木頭です。
渡御祭(祭典中日)
 裃姿の神社役員と八雲講世話人、翌々年当番町(受々当町)若衆世話人と白装束の祭半纏姿の若衆がお神輿を担ぎ各町を練り歩きます。順路は仲町、泉町、屋敷町、元田町、金井町、鍜冶町、日野町の順で、正午までにお仮殿に戻ることが若衆の心意気とされています。
裃姿の神社役員と八雲講世話人、翌々年当番町(受々当町)若衆世話人と白装束の祭半纏姿の若衆がお神輿を担ぎ各町を練り歩きます。順路は仲町、泉町、屋敷町、元田町、金井町、鍜冶町、日野町の順で、正午までにお仮殿に戻ることが若衆の心意気とされています。
笠抜
 その年の最後の山あげのことを指し当番町内で行われます。この笠抜が終わることで当番町の若衆も神輿に参加することが出来ます。(芸題:関の扉、老松)
その年の最後の山あげのことを指し当番町内で行われます。この笠抜が終わることで当番町の若衆も神輿に参加することが出来ます。(芸題:関の扉、老松)
直会
責任役員、奉賛講の代表委員、八雲講世話人一同が拝殿に集まり、夏祭が無事に執行できたことの感謝の行事として行います。お日待ちは各町それぞれの場所で行う直会であり、とても賑やかなものとなり、また、祭礼中のトラブルもこれで一切無しとなります。
またこの日に行われる神輿洗いは、すでに当番の引き継ぎがされているので還御を行った町が当番町として行います。
夏越
 茅輪くぐり、輪くぐり、わっこくぐり等と呼ばれ、蘇民将来の故事に由来します。輪をくぐると夏の虫の災い、頭痛、暑気あたり等の災いを除けるといわれています。
茅輪くぐり、輪くぐり、わっこくぐり等と呼ばれ、蘇民将来の故事に由来します。輪をくぐると夏の虫の災い、頭痛、暑気あたり等の災いを除けるといわれています。
- 2025年8月13日
- 印刷する


