那須烏山市が誇る名産品と一度は行きたいスポットを紹介!
名産品
なすから「コロッケ」物語!?
みなさんご存知ですか?普通、コロッケと言うと牛肉コロッケや野菜入りのコロッケが一般的。しかし那須烏山市の精肉店や食堂などで販売されている「惣菜コロッケ」にはカレー粉が入っているのです。そのため、地元住民はコロッケと言ったら「カレー味」と言う人も少なくないとか。諸説ありますが、江戸末期から昭和初期まで木材、紙、小麦等の水運拠点として栄えた烏山で、当時ハイカラなもの象徴としてカレー粉を入れたのでは?との定説になっているようです。
コロッケの具にカレー粉を入れただけのシンプルなカレー味のコロッケは、地元ならではのB級グルメ。ぜひ、ご賞味あれ!
なすからの「そば」
「そば」は那須烏山市はもとより、この八溝山系ではメジャーな食べものです。
実は、一般的なそば以外にこの地域には「寒ざらしそば」と言うのもあります。これは秋に採れた新そば実を袋に入れ、厳冬期に滝つぼの冷水にさらして、アクを抜いた後、天日と寒風にさらして夏までゆっくり熟成させた特別なそばです。
あまり知られてない手法ですが、一般のそばより雑味がなく、甘みとコシが増して、そばの風味の落ちると言われる初夏から夏場にかけて「新そばの風味」が楽しめます。


なすから焼きそば
この那須烏山市を含め、八溝地区は「蕎麦」が有名です。しかし、一方で「焼きそば」もなかなかのもので、昭和50年代は焼きそば専門店が7店舗ありました。現在は2店舗にまで減少してしまいましたが、焼きそば店としての個性をしっかりと保っています。
専門店としては2店舗ですが、食堂などで売っている焼きそばは「かた焼きそば」や「あんかけ焼きそば」など味に変化をさせて販売しています。
ぜひ、那須烏山市にお越しの際はお立ち寄りください。


ほっこりホクホク「中山カボチャ」
中山カボチャは那須烏山市中山地区で50年以上前から農家が自家用消費に作っていたのが由来とされています。先がとがった紡錘型をしていて、果肉は粉質でホクホクした食感が特徴です。実は栽培するのが難しく、出荷期間も1ヶ月半と短いため、小売価格は通常のカボチャより約3割増し。ブランド志向が高く、平成25年には地域団体商標登録をしました。
平成23年11月には、生産拡大とブランド化を図るため、イオンの「フードアルチザン(食の匠)」活動を活用し、インターネットなどの販売チャンネルを通して、販路の拡大に取り組んでいます。

紡錘型の中山かぼちゃ

中山かぼちゃアイス

中山かぼちゃ・カレーコロッケ
龍門の滝
JR烏山線、滝駅から徒歩5分のところにある「龍門の滝」。江川にかかる幅65m、高さ20mからなる大滝で、滝壺の中に、男釜と女釜の2つの歐穴があり、大蛇が住んでいたと言うことから名付けられ、名称の由来にもなっています。また、滝周辺は遊歩道で整備されていますので、太平寺と併せて那須烏山市の自然と歴史が堪能できます。滝の上にはJRも走っているので、鉄道ファンの間でも有名です。
令和3年には龍門ふるさと民芸館がリニューアルし、龍門カフェが併設されるなど市民や観光客の憩いの場となっています。
※火気の取扱いは禁止です。





龍門ふるさと民芸館

龍門カフェの人気商品 ベーグル

滝が見えるテラス席
烏山城
応永25年(1418)、那須氏一族の沢村五郎資重によって築城されたと言われる烏山城。その後は、織田・成田・松下・堀・板倉・那須・永井・幕府代官・稲垣氏と短期間のうちに城主が交替しましたが、享保10年(1725)大久保常春入封の後、大久保氏が8代140年余にわたり城主を勤め、明治2年(1869)の版籍奉還とともに廃城しました。
烏山城は、町の中心より北西に位置する八高山に築かれた山城で、山の形が寝ている牛の姿に似ていることから「臥牛城」とも呼ばれています。城域は、東西約370m、南北約510m、面積約88haに及ぶ広大なもので、肥前や「かわらけ」と呼ばれる素焼きの皿も発見されています。また、同一の城で石積みの手法が3種類混在しているのは、専門家や城マニアにとっては大変珍しい城跡として知られています。
平成30年には築城600年を迎えましたが、城跡には空堀・土塁・石垣などの各遺構が良好な状態で残っています。八雲神社北側から毘沙門山・城山に至る遊歩道が整備されていますので、城跡を見学しながら散策することもできます。

全景

カワラケ出土

三の丸石垣

吹貫門脇の石垣
~関東の嵐山~ 落石の紅葉と雪景色
那須烏山市の中央を流れる那珂川の東岸に位置する落石は、「関東の嵐山」と呼ばれる風光明媚な紅葉の名所です。近代化遺産のアーチ橋「境橋」と八溝山系の紅葉とのコントラストは、まさに絶景の一言。また、冬には雪景色が一層味わい深い風景を演出します。
那珂川は鮎でも有名ですが、紅葉の時期には50Km以上もの旅をした鮭の遡上も見ることができます。ちなみに、例年であれば紅葉の見ごろは11月上旬から下旬です。一度は「関東の嵐山」を見に足を運んでみてはいかがでしょうか?






桜
那須烏山市の桜と言えば、代表的なのが「西山辰街道の大桜」です。樹齢推定350年と言われる山桜。那須烏山市八ヶ代字西山と高根沢町との境の高台にあり、南北に走る辰街道の傍らに咲き誇ります。また、この大桜以外にも那須烏山市内には見事に咲く桜の名所がたくさんあります。お花見はもちろんですが、春のハイキングやサイクリング、ジョギングを楽しむ人には必見です。お越しの際は、ぜひ散策してみてください。

国道294号沿い

ウォーキングトレイル(南那須図書館付近)

ウォーキングトレイル(荒川沿い)

西山辰道大桜

龍門の滝

清水川せせらぎ公園
太平寺
太平寺はJR烏山線、滝駅から徒歩5分のところにある「龍門の滝」の隣にあります。
坂上田村麻呂が蝦夷討伐の際に戦勝祈願し、千手観音を安置しました。その後、嘉祥元年(848年)に慈覚大師が開創した古刹といわれています。
23段の石段上にある境内に風格ある豪壮な仁王門が建立されており、この仁王門は、「龍門の滝」の中段にある男釜から出現した大蛇が七巻き半したと伝承されている山門です。この山門にかかる大草鞋の奉納は、足腰・旅路の祈願とされています。江戸時代中期頃の作と伝えられる迫力ある「仁王像」が仏門を守護しています。
また、位牌堂横の盛んに葉を茂らせた巨樹は、樹齢200年余の大木。「太平寺のカヤ」で、栃木県名木百選にも認定されています。
春にはカタクリの群生、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と春夏秋冬を問わず四季を楽しめます。歴史と自然にあふれる太平寺。一度足を運んでみてはいかがでしょうか?

全景

草鞋

太平寺のカヤ

太平寺の仁王門

太平寺の雪景色1

太平寺の雪景色2

太平寺の紅葉1

太平寺の紅葉2
大金吊橋・ウォーキングトレイル
那珂川の支流、荒川に架かる長さ97mの橋で、世界的でも例を見ない珍しい主塔が片側のみの非対象PC構造の吊橋です。付近には、「美しい日本の歩きたくなるみち500選」にも選ばれたウォーキングトレイルが設けられ、ウォーキングやジョギングにはもってこいの場所になっています。対岸の橋の先はちょっとした展望台にもなっているので、眺めを楽しみながら、荒川の雄大な流れを見て心も体もリフレッシュしてみませんか?


「なすから」の方言知ってっけ?
那須烏山市は、通称「八溝地域」に属する地方です。昔から、独特の「言葉のなまり」や「尻上がりの語尾」など、多くの方言があり、本市を訪れる方の中には、「何をしゃべっているか分からない」と言う方もいるかもしれません。ここでは、そんな「なすからの方言」の一部をご紹介します。
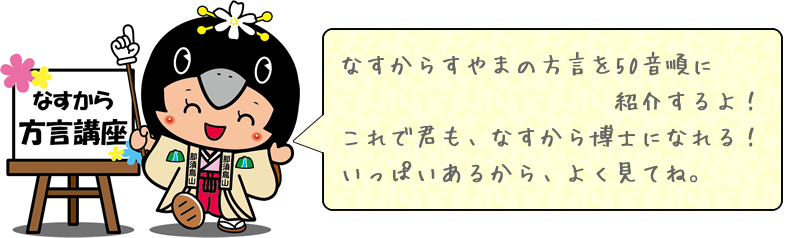
あ行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| あさっぱら | 朝方 | あさま | 朝のうち |
| あしっこ | 足跡 | あったらもの | 惜しいこと |
| あっちさこっちさ | あちらこちら | あづっこい | 厚い |
| あとっちゃり | 後退り | あなっこ | 穴 |
| あなめど | 穴 | あまごや | 倉庫 |
| あまや | 納屋 | あんたげ | あなたの家 |
| あんべわるい | 具合が悪い | いいあんべ | ちょうどよい |
| いいかんべ | いい加減 | いかんべ(いがんべ) | いいだろう |
| いがい | 大きい | いきゃーす | 行きます |
| いしこい(いしけい) | 粗悪・悪い | いたっぱじ(いたっぱち) | 小さな板 |
| いってすける(いってつける) | 一緒に行く | いでる | 凍る |
| いぶい | 煙たい | いまっと | もっと |
| うそこく(うそこけ) | 嘘を言う、嘘を言うな | うっちゃる | 捨てる |
| うめえ(うんめい・うんまい) | おいしい | うんと | たくさん |
| ええ | 良い | えかんべ(えがんべ) | いいだろう |
| えしけぇ | 粗悪、悪い | おおがん | 道路 |
| おゆはん | 夕食 | おおがんまわし | 洪水(冠水により河川が氾濫しそうなさま) |
| おがげなせ(おがげなんしょ) | 座ってください・お座りください | おがめぇはりやすんな | おかまいなく |
| おごれ(おこれ) | ください・ちょうだい | おごわ | 赤飯 |
| おしゃんこ | 正座(一般的には座ること) | おそっこわい | 疲れる・面倒 |
| おっかく(おっがく) | 折る・壊す | おっかねぇ(おっがねぇ) | 恐ろしい |
| おっこちる(おっこじる) | 落ちる・落とす | おったまげる | びっくりする |
| おっちめる | 押す | おっちょる | 折る |
| おっぴたす | 水につける | おっぴろげる | 広げる |
| おばんがた | こんばんは | おまんま | ご飯・めし |
| おらげ(おらんち) | 自分の家 | おんだす | 追い出す・押し出す |
| おんつぁれる | 叱られる | おまんま | ご飯・めし |
か行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| かぎまし | 炊事 | かけっこ | 競争(走る) |
| かっくらす | 殴る | かっちゃがむ | 座る |
| かっつぁく | ひっかく | かっぱぐ | 剥ぐ |
| かっぺずる | ひっかく | かっぺなす | けなす |
| かっぽる | 捨てる | かつける | (責任を)なすりつける |
| かわっぺり | 川岸 | かわらっぽ | 川 |
| がんがら | 缶 | かんます | かきまわす |
| きかんぼ | 乱暴者 | きっぱじ | 小さな木の枝 |
| きどころね | うたたね | きれっぱし | 布切れ |
| くさっぽ | 草 | くちはび | マムシ(蛇) |
| くっちゃべる | おしゃべりする | くっつく | 噛みつく |
| くらぁねぇ | 大丈夫・何ともない | ぐるわ | 周囲 |
| くれろ | ください(おごれより命令形) | けぇる | カエル |
| げんさんぼ | とんぼ | こうご(おこうご) | 漬物 |
| こじはん | おやつ | ごじゃっぺ | でたらめ、いい加減 |
| こずく | 軽く叩く | こそっぱい | 質が粗い |
| ごっこと(ごっごと) | さっさと | こでっちり(こみっちり) | たくさん |
| こでらんねぇ | こんな良いことはない | こねくる(こねぐる) | いじりまわす |
| こわい | 疲れる | ごんど | ごみ |
| こんまがる | まえにかがむ |
さ行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| さがんぼ(しゃがんぼ) | つらら | ささらほさら | まとまりがなく、だめにする |
| さぶろ | シャベル、スコップ | されかまね | かまわない |
| さんざっぱら | 十分、さんざん | しこる | 格好つける |
| しっちばる | 縛る | しりっぺた | 先端・端の方 |
| じなる | 怒鳴る | しめぇ | 終わり・最後 |
| しゃある | 退く | しゃくご | ものさし |
| しゃじ | さじ・スプーン | じゃっちゃかぶり | 大雨 |
| じゃんがら | 馬鈴薯 | しょう | 背負う |
| しょっぺい | 塩辛い | しょうがあんめ(しゃあながんべ) | 仕方がない(だろう) |
| すく | 敷く(布団を敷くなど) | すっかい(すっけぇ) | すっぱい |
| すみっこ | 隅 | ずずねぇ | 気持ちが悪い・具合が悪い |
| せいふろ | お風呂 | せいる | 仲間に入れる |
| そばえる | 甘える |
た行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| たけつっぽ(たかすっぽ) | 竹筒 | だいじ | 大丈夫・平気 |
| ちく | うそ | ちくらっぽ | 嘘をつく |
| ちちっぺら | 土塊 | ちっちめ | 魚 |
| ちめてぇ(ちゃっこい) | 冷たい | ちゃある | 捨てる |
| ちっけい(ちっこい) | 小さい | ちゃっぽ | 帽子 |
| ちゃぶす | 潰す | ちょうずば | トイレ |
| ちょごっと | ほんの少し | ちょっくら | ちょっと |
| ちょっぴた | 丁度・ぴったり | ちんちめ | すずめ |
| つっかけ | サンダル | つっぺる | 水の中に落ちる |
| つんだす | 差し出す | つんのめる | 前に倒れる |
| つんむぐる | 潜る | でいじぐさま | 大神宮様 |
| てぇら | 人たち | てぬげ(てのごい) | 手拭 |
| でほらく | 冗談 | でれすけ | ばか者 |
| でんぐる | 捨 | とうど | いつも、しょっちゅう |
| とうみぎ | とうもろこし | とっとめ | 鶏 |
| とっぽい | 生意気 | どどめいろ | 青紫色(唇が青紫色になっている状態の時使う) |
| とばくち(とばぐち) | 入口 | とぼ(とんぼ) | 戸() |
な行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| なす | 産む(卵を産むこと) | なめっけい | なめらか |
| なんちゃねぇ | 簡単だ | なんぼにも | なんとしても |
| ねじくれる | すねる | ねっころがる | ねる・横になる |
| ねごんぼ(ねごんご) | 寝ている子、よく寝る子 | のがっぽい | 喉や肌がいがらっぽいこと |
| のっける | のせる | のっぺり(のっぺら) | なめらか、たいら |
| のめる | 埋まる、沈む |
は行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| はしっぺ | 末端 | ぱっかた | 固い |
| ばっちい | 汚い | はねっこ | いなご |
| びしゃくれる | 脅かす | ひっくりげっちょ | 裏返し |
| ひっこぎる | くじく | ひっぱたく | 張り倒す |
| ひっぺがす | 剥がす | ひでなし | 価値がない |
| ひゃっけい(ひゃっこい) | 冷たい | ひゃあもしない(ひゃもしない) | 全く価値がない |
| ひょおげる | ふざける | ひょごる | 勢いよく飛ぶ |
| びりっけつ(びりっかす) | 一番最後 | ひんまげる | 折り曲げる |
| ぶくっちょ | 不器用 | しょったかり(ぶしょってい) | 無精である |
| ぶちかる | 座る | ぶっける | 倒れる |
| ぶっつぁく(ぶっざく) | 割る | ぶっつぁける(ぶっざげる) | 破れる |
| ふったける | 火を付ける、物事を煽る | ぶっちゃす | 壊す、潰す |
| ぶっちょる | 折る | ぶっとうし | 連続して |
| ぶっちらかす(ぶっぴろげる) | 散らかし広げる | ふんごむ | 入る、足を入れる |
| ふんじゃす(ふんずぶす) | 踏み潰す | ふんぬき | 釘などを踏む、踏んでケガをする |
| ぶんぬき | そっくり | へたっかす(へだっかす) | 不器用、上手にできないさま |
| へっぺがす | 剥がす | へんまげる | 折り曲げる |
| ほうげえ(ほうげ) | そうですか、そうかい? | ほうろかす | 揺り動かす |
| ぼさっこ | 藪 | ほじくる | 掘る |
| ほそっこ | 紐 | ぼっこす | 壊す |
| ぼっこれ | 壊れたもの | ほったらこと | そんなこと |
| ぼっとすっと | ひょっとすると | ほっぺた | 頬 |
| ほっつく | ぶらぶら歩く | ほりっこ | 小堀 |
ま行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| まじっぺ | まぶしい | まぜろや | 仲間に入れてくれ(命令形) |
| まどろっこい(まどろっこし) | 動作が鈍い | むぐれる | すねる、へそを曲げる |
| むこうさ | むこうへ | むそい | 長持ちする |
| むぐる | 漏れる | めど | 孔、穴 |
| めなし | あかぎれ | もがり | 生垣 |
| もそい | 長持ち | もっさり | 繁っている |
や行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| やまがじ | やまかがし | やまっき | 野良着 |
| やれや | ○○しなさい、物をあげなさい | やんながんべ(やんねべ) | ○○することはやめよう |
| ゆうぐし | 魚の串 | ゆっくら | ゆっくり |
| ゆつけおび(ゆつこび) | 背負い帯 | よいっぱか | ゆい(相互作業) |
| よこっちょ | 脇の方、脇のあたり | よせっこ | 側 |
| よっぱら | 沢山 | よっぴで | 夜通し |
わ行
| 方言 | 意味 | 方言 | 意味 |
|---|---|---|---|
| わすらする | もてあそぶ | わたまし(わたまわし) | 新築祝い |
| わっこ | 輪 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1151 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年8月23日
- 印刷する